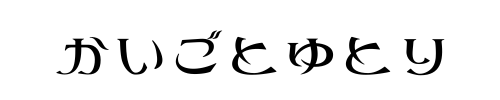✔「トイレに行く」ってスゴイこと
今日は名古屋の天気は曇天です。
最強寒波らしいです。皆様どうかご自愛くださいね。
本日は、認知症排泄ケアの「環境づくり」についてです。
いろんな人からアドバイスをもらったり、仕事としてやってみたりして、
よかったことを書いてみます。
「ちょっとトイレ行ってくる」
と、私は毎日何回もトイレに駆け込みます。
でも、認知症の人にとって、トイレは作業が多くて混乱し、
結果「一人でできない」となってしまいます。
まず尿意便意。
おしっこ・便が出る、と自分で感じる。
次にトイレまで行く。
ドアや階段があって大変。
場所もようわからん。
トイレに着いたら便器を使う、服をおろす。
どうやって座るの?服脱ぐの?
いきむ。
「うーんして」って言われてもね…。
お尻をふく、トイレットペーパーを使う。
紙があるみたいだけど、どうやって拭くの?
服を上げて流して手を洗う。
便器で手洗っていいの?
元の場所に戻る。
どこから来たのだったかな。
数え上げればキリがありません。
この複雑な工程を、私たちは一瞬で判断し行っています。
この工程を楽にする第一歩が環境整備。
物理的に無理なこともあると思いますが、
何かの参考になれば幸いです。
余談ですが、認知症の人がトイレの工程を理解できないのは、
私たちが外国へ行って、
場所も便器も全然違う時に戸惑うのと一緒かな、と感じます。
アメリカなんて足元丸見えだし、中国は扉がないらしい。
どうしろっていうんだ。
✔私の環境づくり
動線の簡素化
狭い我家でもドアはあります。笑。
私は、母の部屋からトイレまでの動線上にある物を撤去しました。
トイレへの道のりを最短にするためです。
・廊下のドアを外す。
(寒いので暖簾や断熱材で防寒する)
・トイレのドアは24時間開けっ放しにする。
(閉めるときはトイレと大きく書いた張り紙をする)
・トイレの蓋も開けっ放しにする。
・床緩衝材などで段差をなくす。
ポータブルトイレを置くことも考えましたが、
今までの人生で使ったこともないポータブルトイレ自体が理解できず、
更なる混乱を招くと思って止めました。
また、お住まいの環境では、本人が2階にいることも多いと思います。
2階にトイレがあればいいのですが、
そうでなければ、早い段階で、もう明日にでも本人を
1階(トイレの近く)に移動させる方がお互いに楽です。
認知症は環境の変化に弱い、と言いますが、
トイレの混乱が出始めたころなら、
自宅内の移動なら、充分に対応できると思います。
多分、移動してしばらくは、激しく文句を言われますけど…。
一人で降りてきてまでトイレに行こうとする人は、
ポータブルトイレは、まず使わないです。
何より、一人で階段を降りて転倒するリスクが減ります。
しかし、1階は一人で徘徊に出て行ってしまうリスクが増えます。
施錠対策をしっかりしてくださいね。
「本人のいる時代」のトイレに近づける
高齢者は子供時代、くみ取り式トイレで育っています。
くみ取り式時代の物を少し取り入れると、
意外に動作がすんなりいく場合もあります。
・トイレットペーパーをチリ紙にする。
・お尻を拭いた後の紙を捨てるゴミ箱を置く。
(紙が流れる概念がないため)
そうは言っても、やっぱり洋式サイコー。
ウォシュレットは、お尻洗いと便秘時の神様ですし。
ウォシュレットのボタンは、誤ってよく押すので、
段ボールなどで覆ってくださいね。
トイレから物をなくす
認知症の人は、なんであんなにトイレットペーパーや
ティッシュペーパーにこだわるのでしょうか。
母だけだと思っていたら、みんなそう。
ずっとカラカラと出し続け、折りたたんだり、丸めたり、剥がしてみたり。
それを絶対にポケットに入れる。
洗濯する時に地獄を見るから、頼むからポッケに入れないでおくれ…。
トイレットペーパーは必要分だけ手渡しです。
それに飽きると、今度はリハパンを剥がし始める。
ポリマー、出るからっ!!
トイレ、詰まるからっ!!
ポッケには入れないで!!
上記のような理由で、とにかくトイレには物を置きません。
タオルも、掃除道具も、準備したリハパンも、
認知症の人からしたら「何?これ?」です。
つい手に取ってみたくなります。
で、結果、トイレが詰まります。
棚にしまっても、特に下方に棚があれば開けて出します。
棚もロックが必要です。
掃除が楽になるので一石二鳥と考えました。
掃除道具を揃える
もう、これ必須。
・泡ハイター
・ゴム手袋、マスク
・新聞紙
・歯ブラシなどブラシ系(大中小サイズ各種)
・雑巾、要らない布やタオル
・バケツ
・ラバーカップ(通称トイレスッポン)
・火ばさみ(詰まった物を取り出すため)
すぐ出動できる場所に、隠してしまってね。
✔それでも事件は起きる 笑
こうやって環境を整えても、事件は絶対に起きます。
たまには、ご本人たちにダイレクト表現で言いたい。
「リハパンは、流れませんヨ」
「便器では手は洗えませんヨ」
「ウォシュレットは全身シャワーではありませんヨ」
「トイレに猛ダッシュで駆け込むのはやめてネ」
「奥まで座らないと、床に全部漏れますヨ」
「畳はトイレではありませんヨ」
…言葉、笑顔で飲み込みます。
トイレはパーソナルスペース。
一部介助ぐらいの人だと、見守る中で一時的にでも目を離します。
介護者は、できることは自分でやって欲しい。
本人も、人に迷惑かけたくないから自分でやりたいと思っている。
きっとお互いそう思っている。
そんな優しい気持ちで頑張った末、失敗しても、もうそれは仕方がない。
さぁ、片付けましょう。
ケガがなくて良かったね。
トイレの大混乱は、だいたい1~2年くらいで納まります。
それは、認知症の進行で、
尿意便意を感じなくなり、
こちらが排泄サイクルをコントロールするようになるからです。
なので、どんなに環境を整えても、
子育てと違って「できるようになるため」ではなく、
「できなくなるけれど、一日でもできる日を保つ」ことが
目的。
できなくても、どうかご自身も認知症の人のことも責めないであげてください。
できることを大切に…。
そして、疲れたらなにかいい香りで、鼻と心をリセット。
ちなみに、私はアロマテラピー1級を持っています。
我家はペットがいないので、
全部掃除したら、アロマやお香を焚きます。
よかったら、ご自身や本人が癒される、
好きなもの、美味しい物の匂いやお花の香りなどを見つけてみてください。
ぶっちゃけ、それでも辛いんだけどね!
うふふふっ!
明日も働くか!